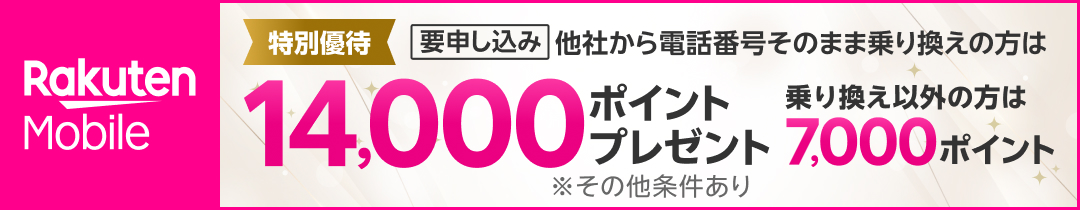萬福寺 まんぷくじ
- 万福寺
黄檗(おうばく)宗の大本山
1659年(萬治2)隠元禅師が徳川四代将軍家綱公より、この地を賜わりました。1661年(寛文1)新しい寺の建立を始め、もともと中国福州府の黄檗山萬福寺の住持であった隠元禅師が、元を忘れないため黄檗山萬福寺を命名しました。中国の明時代の禅文化の影響が多くみられ、京都のお寺の中でもひときわユニークな存在感を放っています。
布袋尊 / 都七福神
国の重要文化財に指定される天王殿の正面にデンと祀られているのが像高110.3cmという布袋尊の坐像が祀られています。中国・唐の時代に実在した、契此(けいし)というお坊さんがルーツとされ、中国では弥勒菩薩の化現として信仰されています。いつも大きな袋をかついで国中を旅していたことから、いつしか「布袋」と呼ばれるようになりました。布袋尊は弥勒菩薩の化身といわれ、黄檗山萬福寺では弥勒菩薩(みろくぼさつ)として祀られています。
福徳円満の神様。
この巨大な布袋尊像の背後に像高200cmという巨大な韋駄天(いだてん)、すべて像高223cmの広目天(西方)、多聞天(北)、持国天(東)、増長天(南)という四方を守護する四天王も祀っています。
これらは萬福寺の玄関となる天王殿に祀られています。この天王殿の×型の組子を入れた匂欄(高欄)は、日本では特異なたすき匂欄で、チベット・中国で使用されているデザインです。ほかの仏教寺院と一線を引く独特の造りは見どころです。
大雄寶殿(だいおうほうでん)
本堂であり、最大の伽藍。日本では唯一最大のチーク材を使った歴史的建造物として、大変重要かつ貴重なものです。本尊は釈迦牟尼佛。両脇侍は迦葉、阿難の二尊者。両脇に十八羅漢像を安置しています。
木魚の原形
斎堂(食堂)前の回廊に吊されている開梛(かいぱん)、魚梆(ぎょほう)とも言われる鳴り物は、時を報ずるための魚板です。貪(とん)・瞋(じん)・癡(ち)の三毒だとも言われる「珠」を口にくわえた鯉で、三毒とは、仏教において克服すべき3つの煩悩だそうで、貪=欲、瞋=怒りの心、癡=愚痴、心理に対する無知、のことだそうです。その形から木魚の原形となったといわれています。
中国伝統の普茶料理
インゲン豆、西瓜、蓮根、孟宗竹(タケノコ)など、様々な野菜を伝承した隠元禅師ならではの精進料理の一種、普茶料理を味わうことが出来ます。見た目の華やかさとともに、ヘルシーな料理として人気を呼んでいます(3日前までに要予約)
御朱印

※いただける御朱印の種類は、期間によって変わる場合があります。
- 所在地
-
〒611-0011
宇治市五ヶ庄三番割34 - TEL
- 077-432-3900
- 正式名
- 萬福寺
- 創建年
- 1661年(寛文1)
- 山号
- 黄檗山
- 宗派
- 檗宗大本山
- 本尊
- 釈迦如来
- 開基
- 隠元隆琦
- 文化財
- 建造物23棟、紙本淡彩西湖図4幅ほか(国・重要文化財)
- 料金
- 大人 500円
小中学生 300円 - 時間
- 9:00~17:00
- 駐車場
- 有り
- 交通アクセス
- JR奈良線「黄檗」駅下車,徒歩約5分
京阪電車宇治線「黄檗」駅下車,徒歩約5分 - 公式Webサイト
- https://www.obakusan.or.jp/
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。