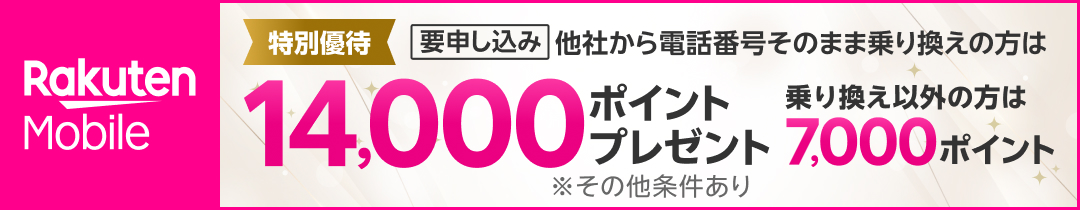Photo by kojiro
kojiro
@kojiro
2014年07月21日
洛陽六阿弥陀巡拝(らくようあみだめぐり)の四番札所「安祥院」
浄土宗 安祥院(あんしょういん)
京都市東山区五条通東大路東入遊行前町にある「安祥院」(あんしょういん)は天慶五年(942年)朱雀天皇の勅願によって、天台座主尊意僧正が乙訓郡大藪郷(現在の京都市南区久世大藪町)に創建した大薮山仁王護国院という天台宗寺院が始まりといわれています。
平安時代から江戸時代まで荒廃と復興を繰り返した後、享保十年(1725年)に木食僧(もくじきそう:五穀を断ち木の実を食する木食行を修する僧)の養阿(ようあ)上人によって再興されました。
現在は阿弥陀如来をご本尊とする浄土宗の寺院です。

Photo by kojiro
日限地蔵尊(ひぎりじぞうそん)
境内の地蔵堂には、養阿上人が享保十五年(1730年)に霊元天皇らの寄進を受けて造った2.6メートルにもおよぶ金銅製半跏像の地蔵尊が安置されています。
このお地蔵様は、日数を決めて(限って)願い事をすれば必ずその願いが叶えられるとする信仰から日限地蔵尊(ひぎりじぞうそん)と呼ばれています。
通常は一般公開されていない安祥院ですが、無病息災、家運隆盛、諸願成就を得ることができるという洛陽六阿弥陀巡拝(らくようあみだめぐり)の四番札所であることから、彼岸と毎月の功徳日には本堂の阿弥陀如来を拝むことができます。

Photo by kojiro
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。