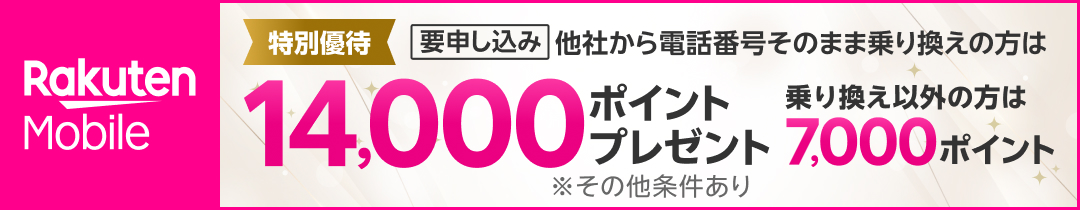迷いの窓、悟りの窓「源光庵」
臨済宗から曹洞宗に
平安時代には都の中心を南北に延びていた朱雀大路、現在は千本通りとその名も変わり北区鷹峰まで続いています。
京の街を南北に延びる千本通りは、今宮通りと交差する辺りから鷹峯街道(たかがみねかいどう)とも呼ばれています。
緩やかな上り坂の鷹峯街道を上がった先に、今回ご紹介する鷹峰山寶樹林源光庵(ようほうざんほうじゅりんげんこうあん)があります。
源光庵は室町時代(南北朝時代)に、大徳寺の徹翁義享(てっとうぎこう)禅師が隠居所として開創した臨済宗大徳寺派の寺院でした。
その後、衰微したこの寺は元禄七年(1694年)加賀国大乗寺の卍山道白(まんざんどうはく)禅師によって再興されたことで、曹洞宗の寺院となりました。

自問自答し自分を見つめなおす二つの窓
元禄七年(1694年)、卍山道白に帰依した金沢の富豪中田静家の寄進により建立された源光庵の本堂には、「迷いの窓」と名付けられた角窓と「悟りの窓」と名付けられた丸窓があります。
「迷いの窓」は四角い窓に「人間の生涯」を象徴し、生老病死(しょうろうびょうし)、愛別離苦(あいべつりく)、怨憎会苦(おんぞうえく)、求不得苦(ぐふとくく)、五蘊盛苦(ごうんじょうく)の四苦八苦を顕わしているといわれています。
「悟りの窓」は円い窓に「禅と円通」の心を表し、ありのままの自然な姿、清らかで偏見のない姿、悟りの境地を教える窓といわれています。
この二つの窓は、まず迷いの窓の前で自問自答し、そのあと悟りの窓の前で自分を見つめ直すことで、純粋な本来の自分に変わることができるといわれています。
この二つの窓の前には、自問自答し自分を見つめなおしている多くの参詣者の姿があります。

アクセス
京都駅から市営地下鉄烏丸線に乗り北大路駅で市バス北1系統に乗り換えます。
源光庵前で降りると西歩いて1分ほどで源光庵の参道があります。

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。