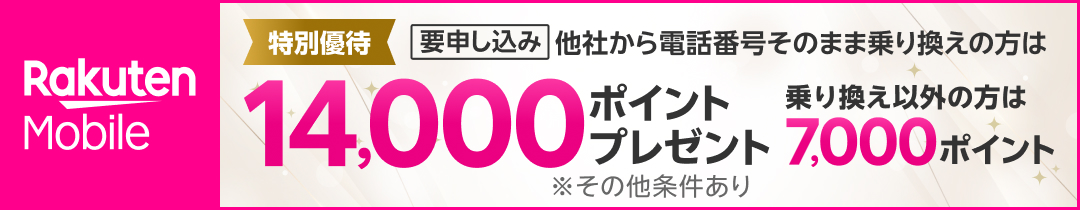独特の工法で組まれた光悦垣「光悦寺」
本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)
大虚山光悦寺(たいきょざんこうえつじ)がある洛北鷹ヶ峰の地は、元和元年(1615年)に徳川家康よりこの地を与えられた本阿弥光悦が移り住んだ所です。
本阿弥光悦の生家である本阿弥家は、室町時代から刀剣を鑑定してきた名家であったことから、光悦は幼いころから家業を通して、あらゆる工芸(木工、金工、漆工、皮細工、蒔絵、染織、螺鈿)知識を身に付けたそうです。
その後、父が分家となり家業から自由の身になった光悦は、工芸品以外にも書画や能面、庭など、さまざまな芸術作品を創造するようになったといわれています。
家康から九万坪ともいわれる鷹ヶ峰の地を与えられた光悦は、ここに草庵を建て本阿弥一族や芸術仲間、弟子、職人衆と共にこの地に移り住み、一時は55軒もの屋敷が並ぶ芸術村を作ったそうです。
現在の光悦寺は、本阿弥家の先祖供養が行われていた位牌堂(位牌所)があった場所といわれています。

光悦垣
光悦寺にあるこの竹垣は、光悦が晩年を過ごしたといわれる大虚庵の路地と光悦寺の境内を仕切っています。
矢来風に菱に組んだ組子の天端を割竹で巻いて玉縁とした光悦寺独特の垣、垣根の高さは親柱からなだらかなカーブを描き端部が低くなっています。
平面的な部分と立体的な部分の調和がとれた光悦好みのこの竹垣は、現在ではさまざま場所で見ることができます。
紅葉の枝が垂れ風情のある光悦垣は秋にレポートさせていただきます。

アクセス
京都駅から市営地下鉄烏丸線に乗り北大路駅で市バス北1系統に乗り換えます。
源光庵前で降りると西歩いて3分ほどで光悦寺の参道が見えてきます。

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。