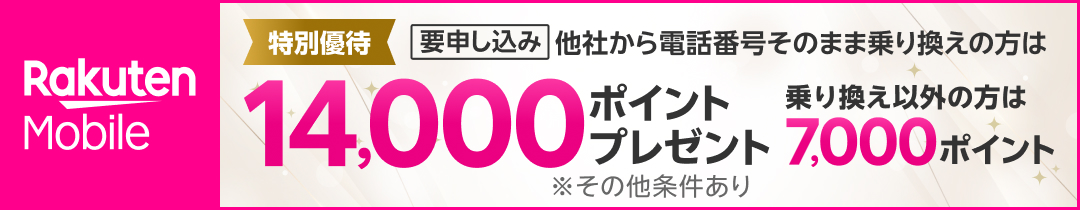京都の庭園30選 〜東福寺界隈~
来迎院(東山)
妙心寺の塔頭のひとつで、織田信長の孫にあたる津田秀則によって創建されました。
枯山水の坪庭「清浄の庭」、露地庭「侘びの庭」、方丈庭園「思惟の庭」「真如の庭」と名付けられた趣の異なる4つの庭は、国の名勝及び史跡に指定されています。いずれも苔が美しく緑一色でも美しい庭園ですが、春には躑躅や皐月、晩秋には紅葉が彩りを添えます。


雲龍院
真言宗泉涌寺には九つの末院があり、雲龍院はその末院の一つです。
本堂の龍華殿、寺宝の土佐光信筆の「絹本着色後円融院宸影」は重要文化財指定。龍華殿では、写経体験(抹茶付)もできます。
禅における悟りの境地を表すという、書院の丸い窓(悟りの窓)と四角い窓(迷いの窓)も有名。春には紅梅や桜、秋には紅葉など窓から楽しむことができます。


天得院
臨済宗東福寺塔頭の一つ。一度は徳川家康に取り壊されましたが、天明9年(1789)に再建されました。
桃山時代に作庭された一面苔の枯山水庭園では、6月から7月にかけて約300本の凛と咲く桔梗の青や白の花が美しく「桔梗の寺」として知られるようになりました。
また、紅葉やツワブキも美しいことで有名で、本堂内の華頭窓と呼ばれる独特な形をした窓を通して楽しむことができます。


芬陀院
東福寺の塔頭のひとつで、創建して以来、一條家の菩提寺となっています。
雪舟作と伝わる庭があることから「雪舟寺」の愛称で知られていおり、庭は鶴亀が配された優美な苔庭で、亀石が夜毎動いたという伝説もあるとか。
書院の背後にある茶室、図南亭は茶関白といわれるほど茶道を愛した一條恵観の好みといわれ、遺愛の勾玉(まがたま)の手水鉢も残されています。茶室の円窓からの眺めは実に趣があり、心が癒やされるでしょう。


光明院
東福寺塔頭で、庭の苔がとても美しいことから「虹の苔寺」として知られている寺院です。
昭和14年に完成した「波心庭」は、昭和の庭造りの名人・重森三玲の作で、仏様に見立てた中央の三つの石(三尊石)から放射状に放たれる光の先にランダムに石が据えられています。白い砂は海、苔の州浜に散らばる白い石は波しぶき。ダイナミックに刈り込んだ背後のサツキやツツジは、雲を表現しています。借景の木々に囲まれた空間に広がる曲線と、岩々のコントラストが印象的な枯山水庭園です。


※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。