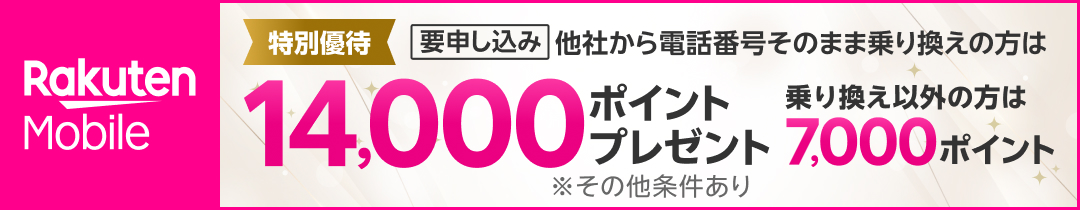黄梅院 おうばいいん
大徳寺の塔頭のひとつ黄梅院
永禄5年(1562年)に織田信長が父・信秀の追悼供養のために春林宗俶(大徳寺98世)を迎えて創建、黄梅庵と名付けられました。庵名は、弘忍大満ゆかりの中国黄梅県破頭山東禅寺に由来します。
天正18年(1582年)の本能寺の変で信長が急逝し、その葬儀が羽柴秀吉により大徳寺で盛大に行われた際、秀吉は信長の塔所として黄梅庵を改築しましたが、主君の塔所としては小さすぎるという理由から大徳寺山内に総見院を新たに創建しました。
その後、春林の法嗣の玉仲宗琇(大徳寺112世)が入寺し、小早川隆景の帰依を受け、堂宇を整備し黄梅院と改められました。天正16年(1588年)に隆景の援助で本堂が建立され、黄梅院は近世を通じて小早川氏の宗家の毛利氏の保護下にありました。院内には毛利家、織田家の墓所のほか、小早川隆景、蒲生氏郷などの墓塔があります。
また、安土・桃山時代、天正年中(1573-1592)、小早川隆景が春林宗俶を開山として創建したという説もあり、没後、その法名により院号としたとも言われています。
貴重な文化財も数多く所蔵されており、本堂中に雲谷派の祖・雲谷等顔(1547-1618)の水墨壁画、室中に「竹林七賢図」十六面(重要文化財)があります。また、檀那の間に「西湖図」十四面(重要文化財)、礼の間に「芦雁図」十四面(重要文化財)、自休軒に雪舟4代・雲谷派の雲谷等益(1591-1644)襖絵八面、北西の間には小田海遷(1785-1862)の襖絵八面があります。
千利休が作庭した「直中庭」
書院南庭は千利休が62歳のころに作庭したとされる「直中庭」があります。一面苔におおわれた枯山水庭園には豊臣秀吉が希望した瓢箪をかたどった池があり、加藤清正が持ち帰ったといわれる朝鮮灯籠が据えられています。
桃山時代の戦国大名、文化人と非常に深い繋がりを感じることができます。
- 所在地
-
〒603-8231
京都府京都市北区紫野大徳寺町83-1 - TEL
- 075-492-4539
- 創建年
- 1562年
- 宗派
- 臨済宗大徳寺派
- 開基
- 大徳寺98世・春林宗俶
- 文化財
- 本堂(附:玄関) 庫裏 雲谷等顔水墨壁画 竹林七賢図十六面(重要文化財) 西湖図十四面(重要文化財) 芦雁図十四面(重要文化財) 雲谷等益襖絵八面 小田海遷襖絵八面
- 交通アクセス
- 市バス「大徳寺前」下車,徒歩5分
- 備考
- 通常非公開
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。