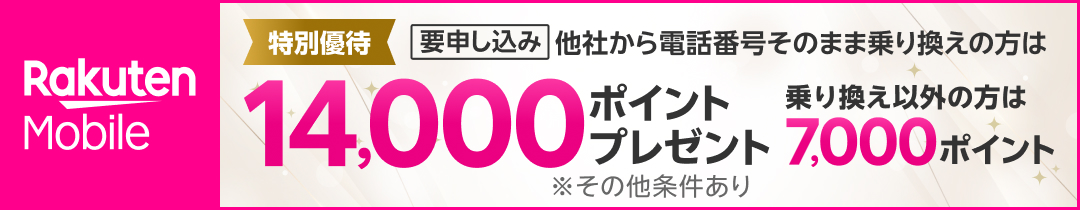養源院 ようげんいん
- 血天井・宗達寺
豊臣秀吉の命により自害を命じられた、北近江の戦国武将・浅井長政。その供養のために、長政の長女だった淀殿の建てた供養寺が「養源院」です。「養源院」の名は長政の法名からつけられました。その後落雷に遭い、焼失しますが、二代将軍徳川秀忠の正室になった三女お江によって再建され、今に至っています。ここには、創建者の淀殿、再建者のお江の肖像画、そして日本史の教科書でよく目にする豊臣秀頼の肖像画があります。特に、お江の肖像画はここでしか見ることができません。
また、お江によって再興された後、養源院は徳川家の菩提所となり、2代将軍秀忠から14代将軍家茂までの位牌が安置されています。お江と秀忠の位牌をよく見ると、「菊」「葵」「桐」の3つの紋があります。3つの紋を拝見できる寺院は日本でここだけです。
血天井
養源院は、本堂の正面と左右の廊下の天井は伏見城が落城した際、家康から同城の守備を命じられ自刃した徳川家の武士たち380余名の血が染みついた板間を用いたものと言われています。俗に血天井と呼ばれています。
俵屋宗達の描く世界
本堂には俵屋宗達が描いた襖絵「松図十二面」や、白象、唐獅子、麒麟を描いた杉戸絵があり、これはすべて重要文化財です。白象図は中学校・高校の美術教科書などにも載っていたことがあるので、見覚えのある人もいるのではないでしょうか。無名の扇絵職人だった宗達は、養源院の絵師に大抜擢され、この杉戸絵で一躍名を馳せることになります。
宗達は屏風絵はいくつか残していますが、襖絵はたったこれだけなので、杉戸絵も併せてどちらも養源院でしか見られません。
うぐいす張りの廊下
本堂にはキュッキュッとうぐいすの鳴き声のような音がする、「うぐいす張りの廊下」があります。江戸時代初期に活躍した彫刻家・左甚五郎の作で、夜間の侵入者を防ぐべく、一種の警報装置の役割を担っています。
- 所在地
-
〒605-0941
京都市東山区三十三間堂廻り町656 - TEL
- 075-561-3887
- 正式名
- 養源院
- 創建年
- 文禄3年(1594年)
- 山号
- 南叡山
- 宗派
- 浄土真宗遣迎院派
- 本尊
- 阿弥陀如来
- 開基
- 淀殿、成伯(開山)
- 文化財
- 金地着色松図、着色杉戸絵(重要文化財)
- 料金
- 拝観料 600円
- 時間
- 10:00~15:00(最終受付14:45)
- 交通アクセス
- 市バス「博物館三十三間堂前」「東山七条」下車,徒歩約3分
京阪電車「七条」駅下車,徒歩約10分 - 公式Webサイト
- https://yougenin.jp/
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。