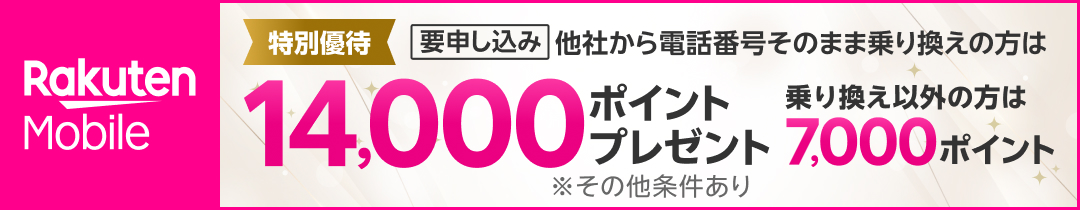山崎聖天 やまざきしょうてん
- 妙音山
- 観音寺
山崎の聖天さん
山崎聖天は、天王山の東側の中腹にあり、正式には妙音山観音寺といい、山崎の聖天(しょうてん)さん」と呼び親しまれています。昌泰2年(899)に宇多天皇の勅願により創建。一時は衰退しましたが、江戸時代に木食上人以空(もくじきしょうにんいくう)が再興し、聖徳太子の作と伝わる十一面千手観音菩薩を本尊とし、堂塔を整備しました。その後、江戸幕府末の禁門の変の際、1864年(元治元年)、長州の尊皇攘夷派の部隊が山崎の地に陣を取ったことにより、戦火に巻き込まれ、観音寺もこの時の戦火によって、事前に避難させた本尊の十一面千手観世音菩薩と歓喜天像以外を残して焼失してしまいました。今日見る建物は明治になって再建されたものです。
本堂に向かって左側に、歓喜天(聖天)を祀る聖天堂が建っています。歓喜天は、財宝や子宝、安産を祈願して祀られる仏教の護法神。江戸時代には、商売繁昌や家運隆盛を祈願して、朝廷や徳川家、住友家や三井家、鴻池家など名だたる豪商をはじめとする商人らが厚く信仰しました。住友家より寄進された青銅製の灯篭は、触れると商売繁盛が叶うともいわれています。
見どころ
境内地の東斜面には昭和初期に植えられた桜が多くあり、春は、桜が咲き乱れ、併せてハクモクレンもとても美しいです。晩秋はモミジやイチョウが鮮やかに染まります。
- 所在地
-
〒618-0071
乙訓郡大山崎町字大山崎小字白味才62 - TEL
- 075-956-0016
- 正式名
- 妙音山 観音寺
- 創建年
- 899年(昌泰2)
- 山号
- 妙音山
- 宗派
- 真言宗系単立
- 本尊
- 十一面千手観音
- 開基
- 寛平法皇
- 料金
- 無料
- 時間
- 9:00~16:00
- 交通アクセス
- 阪急バス「山崎聖天前」下車,徒歩約10分
JR「山崎」駅・阪急電車「大山崎」駅下車,徒歩約20分
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。