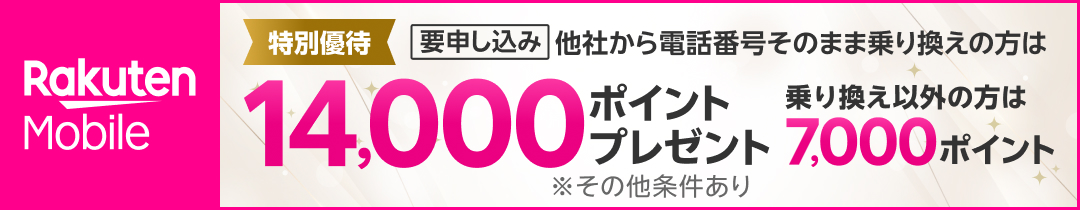禅寺の庭園を巡る ~建仁寺~
建仁寺
建仁2年(1202年)に栄西禅師を開山として創建された京都最古の禅寺です。
応仁の乱などにより荒廃しますが、安国寺恵瓊や徳川幕府の保護により復興しました。
国宝の風神雷神図屏風など、多くの文化財を保有しています。
庭園は方丈の大雄苑のほか潮音庭、〇△□乃庭などがあります。

方丈前庭 大雄苑
方丈の前に広がる枯山水の庭園で、大雄苑(だいおうえん)と呼ばれています。
白砂と巨石と苔でシンプルに作られていますが、その名の通り雄大な庭園です。
庭園の右奥には織田信長の供養塔がみられます。


潮音庭
本坊の中庭で、中央に三尊石を配置してまわりに紅葉を配置しています。
南北の建物、東西の廊下のどの方向から見ても正面に見えるため、「四面正面」の庭ともいわれます。

両足院
約650年前に創建された建仁寺の塔頭寺院です。
創建当初は知足院と呼ばれていましたが、仏の別号「両足尊」にちなんで両足院となりました。
書院前庭の池辺には半夏生が群生していて、半夏生の寺とも呼ばれています。
境内の毘沙門堂の本尊には、黒田長政が関ヶ原の合戦で内兜に収めて戦ったという逸話が残っています。
また、新島八重も禅や茶道を学ぶために両足院へ通ったそうです。

庭園
方丈前には枯山水、書院前には池泉回遊式の庭園があります。
特に書院前庭は半夏生の庭としてよく知られています。

半夏生
七十二候のひとつ、半夏生の頃に葉の半分が白くなります。
別名、カタシログサともいわれます。

正伝永源院
正伝院(鎌倉時代創建)が明治の廃仏毀釈により、永源院(南北朝時代創建)跡地に移転し、
正伝永源院となりました。
細川家の菩提寺で、茶人・織田有楽斎の墓所でもあります。
本堂には狩野山楽による障壁画が飾られていて、国宝・如庵を忠実に再現した茶室があります。

庭園
池を中心とした池泉観賞式の庭園で、池の周りには石組や石橋、刈込を配しています。
春には枝垂桜やつつじ、秋には紅葉を楽しむことができます。

つつじ
特につつじの季節には境内が華やかに彩られます。

アクセス
京都府京都市東山区小松町584
・ 京阪電車「祇園四条駅」より 徒歩 7分
・ 阪急電車「河原町駅」より 徒歩10分

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。