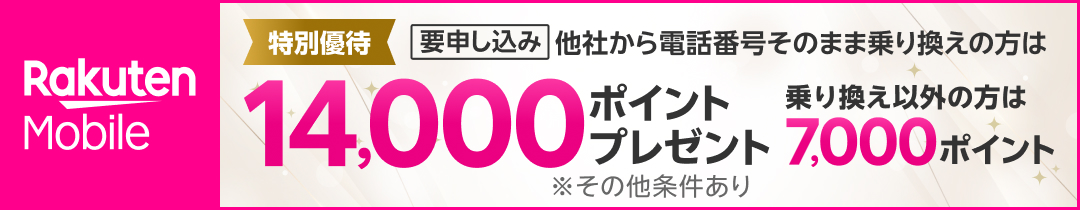東福寺名園探訪
東福寺といえば紅葉の名所、また国宝の三門を筆頭とする雄大な伽藍を連想しますが、数々のモダンな名園でも知られる禅の名刹です。今回は、この庭園を中心に東福寺の魅力をご紹介します。東福寺は、いわゆる東山三十六峰の南端に近い山裾にあり、伏見稲荷大社、泉涌寺、今熊野観音、三十三間堂、京都国立博物館、智積院など、周辺に観光名所が目白押しです。また京都駅からはJR奈良線でほんの一区間、5分程で最寄りの東福寺駅に到着でき、駅から東福寺までは徒歩10分程と、京都駅を起点に観光される方には至近の名所です。
では早速、東福寺の庭園探訪の開始です。我々見学客が境内に到着すると、まずは巨大な三門と本堂がドーンと出迎えてくれます。ちなみに、これらの伽藍は一般公開エリアにありますので、無料で見学できます。

この三門は、大仏様(天竺様)、禅宗様(唐様)、和様を組み合わせたユニークな建築様式で知られ、また室町時代に建造された歴史的文化財のため、国宝に指定されています。楼内には須弥壇があり、釈迦如来像、十六羅漢像が安置されているそうです。
そして三門の奥に聳えるのが本堂(仏殿)、この二つの巨大木造建築が並ぶと壮観ですね。

続いて、こちらが本堂。大正から昭和にかけて再建されたもので、昭和期最大級の木造建築だそうです。また、撮影はできませんが、内部の天井には仏教を守護する雲龍図が描かれています。京都生まれの画家、堂本印象の作品です。

本堂の扁額には”毘盧宝殿”とありますが、”仏という光り輝く宝を安置する建物”という意味でしょうか。

巨大な本堂を仰ぎ見ると、その迫力に圧倒されますね。

ここまでは一般公開エリアのため無料ですが、方丈や通天橋のあるエリアに入るには拝観受付が必要です。写真の庫裏で拝観受付を済ませて、そのまま回廊を進み棟続きの方丈に向かいます。方丈では、東西南北の四面それぞれに個性的な日本庭園が配されています。いずれも、昭和を代表する作庭家、重森三玲が設計した名園で、一見の価値ありです。

方丈に到着すると、まず眼に入るのがこちら。柱石で北斗七星を構成した東庭です。さりげなく白砂の中に配置されているものの、誰しも北斗七星と分かるところが流石ですね。

続いて、方丈の正面に当たる南面の枯山水庭園を見学します。ここで座禅を組むと、少しは悟りに近づけるかも?

ご覧のとおり南庭は長方形の枯山水式庭園で、砂紋が荒海を、また4つの巨石群が蓬莱をはじめとする四仙島を表現します。

南庭の西側には苔むす築山があり、京都五山を表現しています。石組みの厳しい表情と、柔らかい表情の築山という両極端の表現を使うことで、神仙境という非日常的空間を生み出しているようです。

どれも見事な東福寺の庭園ですが、冒頭でご紹介した通り、すべて昭和を代表する作庭家、重森三玲が1939年に設計したものです。当時は重森が作庭家として活躍し始めたごく初期でしたので、彼のデビュー作とも言える庭園群です。重森は全国の500を超える日本庭園を実測・調査した庭園研究家の魁、もともとは画家志望で、活花や茶道の心得もありました。

さて、次は西庭です。この庭園は”井田市松(せいでんいちまつ)”と呼ばれ、その名の通り、格子(チェック)模様を白砂と植木で描写しています。井田は、正方形の土地を九分割(ルービックキューブの一面をイメージしてください)して周囲の八区画を私有財産に、中央の一区画を公有財産にする中国の周時代に施行された土地制度のこと。市松はご存じの通り、格子模様のことです。庭の名前としては難解過ぎるように思いますが、禅の修業の場に相応しい深い意味の名前ですね。

続いて、北庭は”小市松の庭”。西庭の市松模様を細かくしたように、苔と石が小さな格子模様を構成し、さらに西庭から離れるに連れて格子模様が少くなります。そして、最後は庭の東の先の谷に落ちるというストーリーを西庭と合わせて描いているんだそうです。

ともあれ、石に苔という伝統的な素材を使いながら、抽象的なチェック模様を描くとは、なんともモダンな庭ですね。

折角ですから、方丈をぐるっと一周して、再度、南庭の石組みに寄って見ます。これらの石組みには、デビュー作にして、巨石を多用する彼の作風がすでに顕れています。

数ある枯山水庭園ですが、この石組みのように細長い巨石を寝かせたり立てたりする作庭例はほとんどないそうです。重森は単なる模倣者・研究者におわらず、芸術家として独創性も発揮したようです。

方丈庭園を堪能したところで、通天橋のある渓谷、洗玉澗(せんぎょくかん)に向かいます。ここでも拝観受付が必要ですので、料金をお支払いして先に進みます。このまま回廊を真っ直ぐ歩くと通天橋を通って開山堂に行けます。ですが今回は庭が主役、通天橋は後のお楽しみとし、斜面を下って洗玉澗に降りてみましょう。写真の通り、この辺りは一面に楓などの緑の草木が広がり、森林浴にピッタリの場所です。

洗玉澗の底まで降りると、清流のせせらぎに心地よい涼しさを感じます。この、空を覆いつくすような楓が、晩秋には赤や黄に染まるわけですから、東福寺が紅葉の名所になるのも頷けますね。

先程は後回しにしましたが、洗玉澗から空を見上げると、緑の楓に包まれた通天橋を堪能できます。流石は名橋、青空にその姿が映えます。

洗玉澗から見上げた通天橋をもう一枚。少し角度をつけると、観覧用バルコニーを思わせる構造が見て取れます。

洗玉澗を渡ると、谷の斜面に朱色が鮮やかな八角のお堂、愛染堂が見えてきます。その名の通り、愛染明王をお祀りしています。

谷の斜面を登り開山堂に向かうと、途中、枯山水庭園の石組みのような石碑が迎えてくれます。

さらに進むと開山堂が見えてきます。

藤原五摂家の一つ九条家が、19年を費やして天台・真言・禅の各宗堂塔を建立したのが東福寺の始まりだそうです。もともと藤原家の氏寺、法性寺があった所に、東大寺と興福寺を越える大寺院を建立するとして、東福寺と名付けられました。聖一(しょういち)国師を開祖として迎え、1243年に開山。その後、戦火や火災で何度も伽藍が消失したものの、九条家、北条家、足利家、徳川家といった各時代の支配者が援助して再建されました。聖一国師は宋に渡航して禅(臨済宗)を極めた方ですが、天台宗や真言宗の造詣も深く、お茶を出身地の静岡に伝えた功績でも知られます。

開山堂に向かう参道をはさみ、右側は池泉鑑賞式庭園。築山に植木と石がバランスよく配置された所は、智積院の庭園を思い起こさせます。

同じく左側は枯山水式庭園。白砂が碁盤の目になるよう整えられています。

開山堂の庭園は、方丈庭園と異なり抽象性を弱め、より自然と融合した多様性に富んだもので、作庭家 重森三玲の持つ引き出しの多さが伺えます。

参拝を済ませ、改めて庭園を拝見します。タイプの異なる二つの庭園が楽しめるだけに、日本庭園ファンには堪らない見学ポイントです。じっくり堪能できたら、後ろ髪引かれつつ開山堂を後にし、通天閣を渡って一般公開エリアに戻ります。開山堂前の回廊からは、巨大な本堂が正面に見え、改めてその大きさを感じます。

今回の庭園探訪はここで終了。本レポートで東福寺の庭園に興味を持っていただけたら幸いです。私が訪れたのは初秋の9月初旬でしたので、境内を出ると、白壁を背景に真っ赤に咲いた彼岸花が見送ってくれました。

<完>
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。