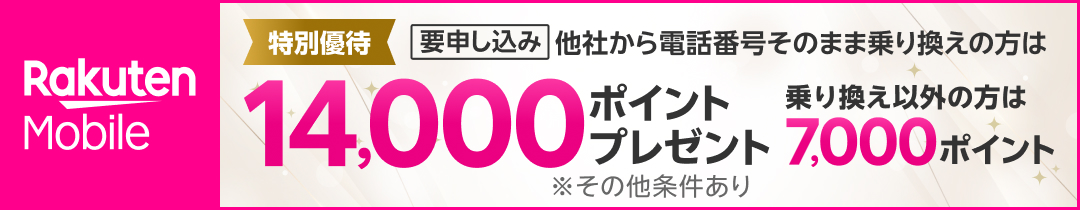京都教育大学 平成29年度 秋季企画展 茶道具が語る戦争 モノから考える平和学習
茶道具が語る戦争と平和
「近代日本の『茶の湯』の営み、なかんずく、そこで使用された茶道具という『モノ』に刻まれた戦争の記憶を題材として、戦争、文化、平和について考える機会を提供」すると解説文にあるように、一般の茶道具展のイメージをはるかに超えた、有意義な時間を過ごすことができました。
大きく、日露戦争と太平洋戦争の二つの戦争と、その後の平和への願いを茶道具を通して知ることができます。
数ある展示品の中からいくつかを取り上げ、展示企画の素晴らしさをお伝えします。

烏城焼詩彫茶碗 渡辺烏城 作
203高地の土を使い、そして乃木希典の七言絶句「爾霊山」が釘彫されています。
「萬人齊仰爾霊山」万人斉しく仰ぐ爾霊山 の一節が印象的です。戦死した兵士を追悼しています。

竹釣舟花入 円能斎 千宗室 作 銘「天祐」
日本海海戦での勝利は、朝鮮戦争から日本への海路の安全をもたらしました。
無事に日本への帰国を果たした人を祝して作られたものです。
舟形の花入はこれまでも見たことがありますが、朱筆で文字が入れられ、かつ尖った先端が、どことなく戦いの舟を彷彿とさせるような、力強い印象があります。

手造日露戦役記念茶碗 箱書 中村虎道 「日露記念」
東西いずれかの本願寺によって戦地に派遣された従軍僧によって、京都に戻ってきてからつくられたそうです。
手捏ねというのも、その人の思いや人柄がより伝わってくるようで、思わず足を止めました。
教科書にない歴史、一人ひとりにとっての戦争がどのようなものだったか、語りかけてくるようです。

羅漢焼茶碗 箱書 渡辺常庵 銘「不動」
明治から昭和前期の茶人、渡辺常庵の箱書です。1945年(昭和20年)3月の大阪大空襲の焼け跡から見つかったそうです。
もとは全面白釉だったのが、高温に触れたことによって赤と緑に一部変色しています。
その変色と器面のようすはきれいでいてどこか恐ろしく、鑑賞しながら緊張してしまいました。
「不動」という銘は、再生の前途を祝してつけられたもの。4,000人が犠牲になった空襲から立ち直る姿のようです。

竹茶杓 近衛文麿作 共筒 「神風」
やはり言葉では語れない何かを持っていて、筆遣いも眺めていると迫りくる感じがします。
どんな歴史も、後世の人間とって振り返ることはたやすいものです。ですが、そのただ中にいた人たちの思いまでは、安易に分析対象にすることはできないのだと感じます。

茶の湯から平和を学ぶ
ともに茶を喫することは、人と人とをつなぎます。用いる道具は深いメッセージ性を持っています。
現在でも、仲良くなりたいならまずは食事からという考えがあるように、やはり「ともに食べること、飲むこと」は大きな役割を担います。
人とのつながりが複雑になれば、それだけ争いのリスクもあがるのかもしれませんが、それでも「和」を唱えつづけ、伝えつづけることは大切だと気づきをいただきました。

ミュージアムをあとにして、ふと見上げると紅葉のグラデーションです。
木々に囲まれた静かな大学構内でした。社会に出ても、人生は一生勉強だなと思う今日このごろ。
「観光」ではどこかものたりない、「研究」は敷居が高い、でも「学び」つづけることはだれにもできます。
知的好奇心に駆られたときには、ぜひ大学へ足を運んでみませんか。

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。