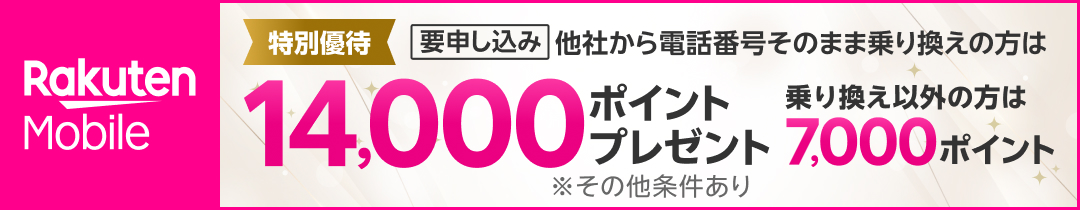新熊野神社 いまくまのじんじゃ
- 権現さん
京都三熊野社 / 新熊野神社
平安時代、紀伊半島南部にある熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の熊野三山を参拝する「熊野詣」が流行していました。しかし、当時の都の人が熊野に参拝することはとても容易ではありませんでした。そこで、熊野の神を京に勧請するよう、後白河上皇が平清盛に命じ、土や木材などを熊野から調達し、造営したのが始まりです。
この新熊野神社のほかに、熊野神社・熊野若王子神社を併せて「京都三熊野社」と呼ばれています。
「新熊野」を「いまくまの」と呼ぶのは、紀州の熊野を古い(昔)とし、京の熊野を新しい(今)と呼んだことが由来です。
能楽発祥の地
能楽の祖の観阿弥・世阿弥父子は、この新熊野神社で「新熊野神事能楽」を披露しました。これを観ていた足利三代将軍義満はとても感動し、2人を観阿弥・世阿弥と名乗らせることになった機縁の地です。境内には『能』と刻まれた記念碑が置かれています。この文字は、世阿弥直筆の著書から採ったものです。
おなかの神様 大樟さん
遠くからでも神社の位置がわかるほど大きな樟(クスノキ)が、鳥居の左側にあります。後白河上皇が植えたと伝えられており、樹齢900年のこの樟は京都市の天然記念物に指定されています。この樟は、おなかの神様と親しまれており、おなかが弱い人がさすると良いとされています。また、安産のご利益があるとも言われています。近くには分身の「さすり木」もあり、多くの人々にさすられ親しまれてきている証拠に、とてもツルツルしています。
御神木 椥(なぎ)の木
新熊野神社は古くから「梛の宮」と呼ばれ、本殿の左右には御神木の椥(梛)があります。昔から、梛は災いをなぎ払うといわれ、平和を招来するといわれてきました。また、梛の葉は切れにくいことから縁結び、二つ並んで実をつけることから夫婦円満のご利益があるとされています。
また、神社周辺の地名「椥ノ森」から、この辺は梛の木が生い茂っていたことが伺えます。
御神鳥 八咫烏(やたがらす)
八咫烏は、別名「太陽の使者」ともいわれ、勝利に導く幸運のシンボルとされています。また、日本サッカー協会のシンボルとしても有名で、サッカーをはじめ、球技愛好者が全国から訪れます。
- 所在地
-
〒605-0971
京都市東山区今熊野椥ノ森町42 - TEL
- 075-561-4892
- 正式名
- 新熊野神社
- 創建年
- 1160年(永暦1)
- 御祭神
- 熊野牟須美大神
- 例祭
- 5月5日
- ご利益
- 健康長寿・病魔退散・技芸上達
- 文化財
- 大樟(市・天然記念物)
- 料金
- 拝観自由
- 時間
- 9:00~17:00
- 駐車場
- 無し
- 交通アクセス
- 市バス208系統「今熊野」下車,徒歩約3分
京阪電車「東福寺」駅下車,徒歩約12分 - 公式Webサイト
- http://imakumanojinja.or.jp/index.html
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。