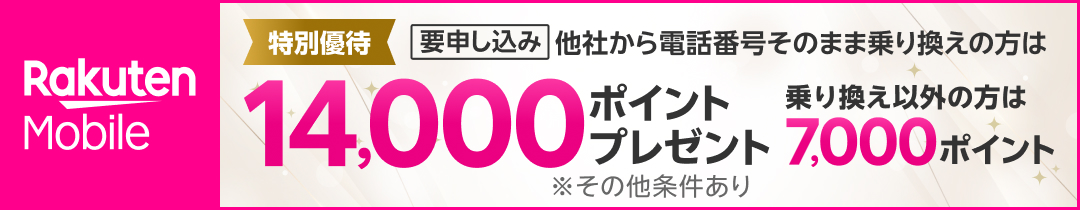京都の紅葉~ 大原界隈~
京都 大原界隈の紅葉の名所を散策します。
寂光院
1186年(文治2)4月、後白河法皇が壇ノ浦で平家が滅びた後、洛北寂光院に隠棲された建礼門院を訪ねられたことは「平家物語」の謡曲「大原御幸」に謡われています。ここ寂光院の本尊は聖徳太子御作の地蔵菩薩で、その左に建礼門院の木像や阿波ノ内侍の張子の座像が安置されています。
四方正面の池が本堂の東側にあり、四方どの面から見ても美しく、池の中を鯉が優雅に泳ぎ、水の音が耳に心地よい小さな滝があります。周囲を回って四面から見られるように小径がつけられています。

三千院
自然の地形を巧みに利用した境内には、豊臣秀吉の建立と伝える客殿や宸殿が建ち、有清園・聚碧園と呼ばれる2つの美しい庭園があります。敷き詰めた苔に散り落ちた赤や橙の色模様も見事。門前もカエデのトンネルで、頭上を覆う紅葉にも感激します。

宝泉院
宝泉院には、盤桓園(ばんかんえん)、鶴亀庭園、宝楽園の3つの庭園があります。
額縁庭園として様々な角度から鑑賞する紅葉は見事の一言です。

来迎院
来迎院は、平安時代前期、聖応大師良忍(りょうにん)上人が建立した、天台声明の音律の根源の地です。
1109年(天仁2年)に融通念仏の祖とされる良忍がこの寺に入寺して再興しましたが、たびたび焼失し、その度に再建され現在の建物は天文年間(1532年-1555年)に再建されたものです。
本堂には重要文化財である藤原時代の「木造薬師如来坐像」「木造阿弥陀如来坐像」「木造釈迦如来坐像」が安置されています。

阿弥陀寺
天然記念物に指定された樹齢約800年の「古知谷楓」が有名です。江戸時代から紅葉の名所として有名で、数百本の楓が赤く色づく様は壮観です。

※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。