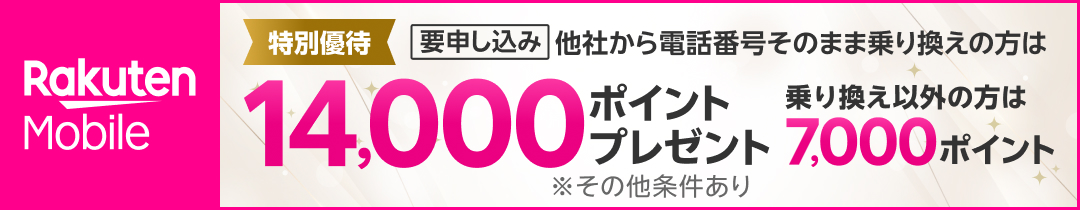魔界スポットめぐり 鞍馬寺
総本山 鞍馬寺 ~義経・牛若のゆかりの地~
鞍馬寺が歴史に登場するのは770年(宝亀1)のこと。寺伝によれば、この年に鑑真和上の高弟、鑑禎上人によって毘沙門天が祀られました。その後の796年(延暦15)に造東寺長官の藤原伊勢人が堂塔伽藍を建立し、千手観世音も合わせて祀られました。こうして、皇室・幕府から庶民に至るまで幅広い信仰を集めてきましたが、昭和22年に鞍馬弘教が立教開宗されて、鞍馬寺はその総本山となりました。
最近では鞍馬寺は天狗が住むと言われるパワースポットとして、また牛若丸こと幼き日の源義経が修行をしたところとして有名です。
「近こうて遠きもの、くらまのつづらおりといふ道」『枕草子』(清少納言)
鞍馬寺にお参りをして帰るコース
大天狗

仁王門

叡山電鉄の鞍馬駅前には、鞍馬に縁のある大天狗が待ち構えています。鞍馬駅から徒歩3分で仁王門が見えてきます。ここから本殿金堂へは徒歩かケーブルカーで行きます。途中、火祭りで有名な「由岐神社」にお参りしたい時は徒歩で行きましょう。
阿吽の虎(阿)

阿吽の虎(吽)

鞍馬寺の狛犬は狛犬ではなく、虎です。虎は御本尊の一尊でもある毘沙門天のお使いである神獣といわれ、毘沙門天ご出現が、虎の月・虎の日・虎の刻であったことから、鞍馬山では特に大切にされているそうです。また、「阿」は口を開いた形で物事の始まりを表し「吽」は口を閉じた形で物事の終わりを意味しており、「阿吽」で万物すべてを表されているそうです。
宇宙エネルギーを受け取ろう
本堂金堂

金剛床

宇宙の大霊、真理そのものである尊天を、御本尊として信仰しているのが鞍馬寺です。尊天の働きを象徴する月輪の精霊ー愛を千手観音菩薩、太陽の精霊ー光を毘沙門天王、大地の霊王-力を護法魔王として、三身を一体の尊天と称され、秘仏御本尊となって本堂に奉安されています。
本堂前に構える虎は、毘沙門天王の出現が虎の月、寅の日、寅の刻と言われることから、御本尊のお使いの神獣とされています。御本尊は、六十年に1度ある、丙寅の年に開扉されます。
宇宙エネルギーである尊天の波動が、果てしなく広がる星曼荼羅を模した金剛床は、天のエネルギーが集まる最強のパワースポットと言われています。
金剛床の中心に立ったなら宇宙そのものである尊天と一体化し、そのエネルギーを感じ取ることが出来るとされています。「山川草木悉皆成仏」という教えを体現するために、金剛床の中心にある六芒星の上に立ってみましょう。
鞍馬寺からさらに上を目指し「貴船」に抜けるコース
※歩いて約2時間程の高低差が大きいハイキングコースとなっておりま。ハイキングに適した服装でお出かけ下さい。
義経(牛若丸)の修行地を辿ろう
奥の院参道の入り口

義経公息つぎの水

小さな門をくぐると、険しい奥の院参道となります。牛若丸は、天狗に兵法を習うために深夜、独りで奥の院道を急ぎ、途中で息つぎのために湧水を飲んだとされています。
木の根道

さらに奥を目指し歩き続けると木の根道に出ます。根が地表面でアラベスク模様を描いています。これはこの辺り一帯の砂岩が、灼熱のマグマの貫入によって硬化したために根が地中に潜れず、地表を這うようにして伸びたようです。ここで牛若丸が修行したと伝えられています。
義経堂

鞍馬山で修行を積み、元服した後は源氏の武将として活躍し、奥州で非業の死を遂げた義経の御魂は、懐かしい鞍馬山に戻り安らかに鎮まっていると伝えられ、遮那王尊として祀られています。この辺りは、牛若が天狗に兵法を習った「僧正ガ谷」です。
魔王殿

奥の院となる「魔王殿」は太古、護法魔王尊が降臨した磐坐・磐境として崇拝されてきました。護法魔王尊は、魔王殿が立つ奇石の上に金星からやって来たとされており、磐座・磐境とされて尊崇を受け続けています。
鞍馬寺 西門

魔王殿から西門をくぐり橋を渡ると、貴船に出ます。貴船神社に歩いて行けるのでそのままお参りして、せっかくなので川床でゆっくりお食事をして帰るのもいいでしょう。
牛若丸と弁慶
義経(牛若丸)の忠臣として有名な武蔵坊弁慶。
二人が五条大橋で出会い戦うことになるのは
義経が修業を終え鞍馬山を降りた後のことです。
そのまま貴船神社へ
貴船神社(本宮)

京都が山背(山城)の国からの水神を祀る社「山城国愛宕郡 貴布禰神社」として記載され、日本の最高位で分祀が全国に約500社ほどあります。ご祭神は高龗神(たかおかみのかみ)です。
貴船神社・結社(中宮)

縁結びの神「結社御祭神・磐長姫命(いわながひめのみこと)」が祀られ、和泉式部の故事を生んだのはこの結社(中宮)です。 奥には和泉式部の歌碑があります。
貴船神社(奥宮)

奥宮の祭神は闇龗神(くらおかみのかみ)を祭神としますが、本宮の高龗神と同じ神であるとされています。
降雨、止雨を司り、降った雨を地中に蓄えて適量湧き出させる動きを司る神様で「龗(おかみ)」という字は「龍」を意味する古語です。
みずうらみくじ

縁結びを願う方はまず本宮で願い事を結び文に書いて結社(中宮)の結び処に結び合わせて祈願して下さい。霊験あらたかで願い事がかない、生涯の幸福が得られると言われています。
お参りの順番は、本宮、奥宮、その帰りに結社(中宮)へと参るのが古くからの習わしです。
- 鞍馬寺
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。