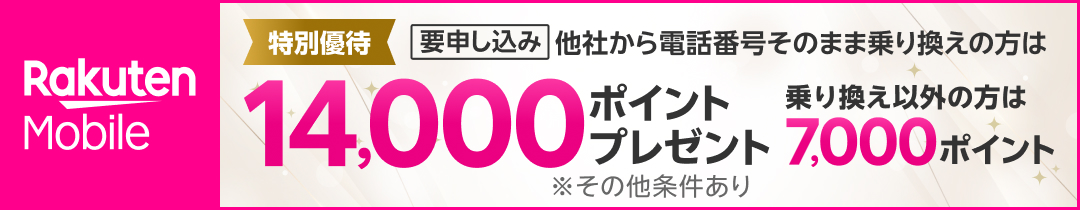六波羅蜜寺 ろくはらみつじ
踊りながら念仏を唱える伝統芸能「踊り念仏」で知られている「市聖空也(いちひじりくうや)」が、平安時代中期(天暦5年)に造立したという「十一面観音」を本尊とする道場に由来しており、当初は「西光寺」と呼ばれていました。
当時、空也上人は、疫病が蔓延する京都で、この観音像を手押し車に乗せ、念仏を唱えながら町を歩き、病人がいれば茶をふるまい、多くの人々を救ったと言われています。
その茶は皇服茶(おうぶくちゃ)、踊躍は六斎念仏として今に伝えられています。
本堂も鎌倉様式を伝える遺構で地蔵菩薩立像は今昔物語にも伝えられ定朝の作と伝えられています。運慶、湛慶坐像もあり、運慶とその子、湛慶、運助の作と言われ、その他、康脇作の空也上人立像、長快作の弘法大師像、閻魔王坐像、平清盛像など鎌倉時代の傑作も多くあります。境内に阿古屋塚や平清盛の石塔もあります。
西国三十三所霊場の第十七番札所でもあります。
平家と六波羅
平安末期、平清盛の祖父正盛が六波羅蜜寺付近に邸宅を構えたことに始まります。清盛の代に至るまで、六道珍皇寺や方広寺を含むこのあたりは平家一門の邸宅が軒を連ねる所となりました。その数は何と最盛期には5200軒余にものぼったとか。
その後保元・平治の乱(1156、1159年)を経て、平家は源氏との争いに敗れて没落してしまいます。そして寿永二(1183)年には兵火に襲われ、六波羅蜜寺の諸堂は本堂だけを残して焼失してしまいました。その後は源頼朝などが再興しましたが兵火により何度も焼失を繰り返す事になります。豊臣秀吉が修造した後は、徳川幕府の寄進で六波羅密寺も広くなりましたが、明治維新後には縮小され今に至ります。
弁財天 / 都七福神
琵琶を奏でるインドの神様で、七福神唯一の女神です。
水を神格化したものであり、美や音楽、技芸、弁舌、学問の神として、また、金運、財運を司る神として信仰されています。
一願石
訪れた人の願いを一つだけ叶えてくれると言われている「一願石」。
石でできた柱の上部には、回転する円盤状の石が取り付けられています。石に書かれている黄金色の文字を正面にして、ぐるぐると三回まわしましょう。その際に、心の中で願い事を唱えると一つだけ叶うとのこと。
御朱印

※いただける御朱印の種類は、期間によって変わる場合があります。
- 所在地
-
〒605-0813
京都市東山区五条通大和大路上ル東 - TEL
- 075-561-6980
- 正式名
- 六波羅蜜寺
- 創建年
- 951年(天暦5)
- 山号
- 補陀洛山
- 宗派
- 真言宗智山派
- 本尊
- 十一面観音(国宝)
- 開基
- 空也
- 文化財
- 木造十一面観音立像(国宝) 本堂・木造空也上人立像ほか(重要文化財)
- 料金
- 令和館拝観料
大人 600円
大・高・中学生 500円
小学生 400円 - 時間
- 8:00~17:00 ※行事によって変更あり
令和館8:30~16:45(受付終了16:30) - 駐車場
- あり
- 交通アクセス
- 市バス「清水道」下車,徒歩約7分
京阪電車「清水五条」駅下車,徒歩約7分
阪急電車「京都河原町」駅下車,徒歩約15分 - 公式Webサイト
- https://www.rokuhara.or.jp/
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。