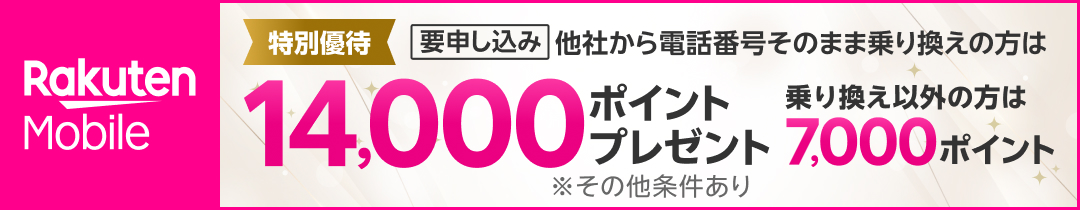よしかわまり
@yossiitomari
- フォトグラファー
- ライター
- 翻訳者
兵庫県在住
女性
※当サイトに掲載の内容はすべて掲載時点での情報です。変更となる可能性がありますので、お出掛けの際は念の為事前にご確認ください。